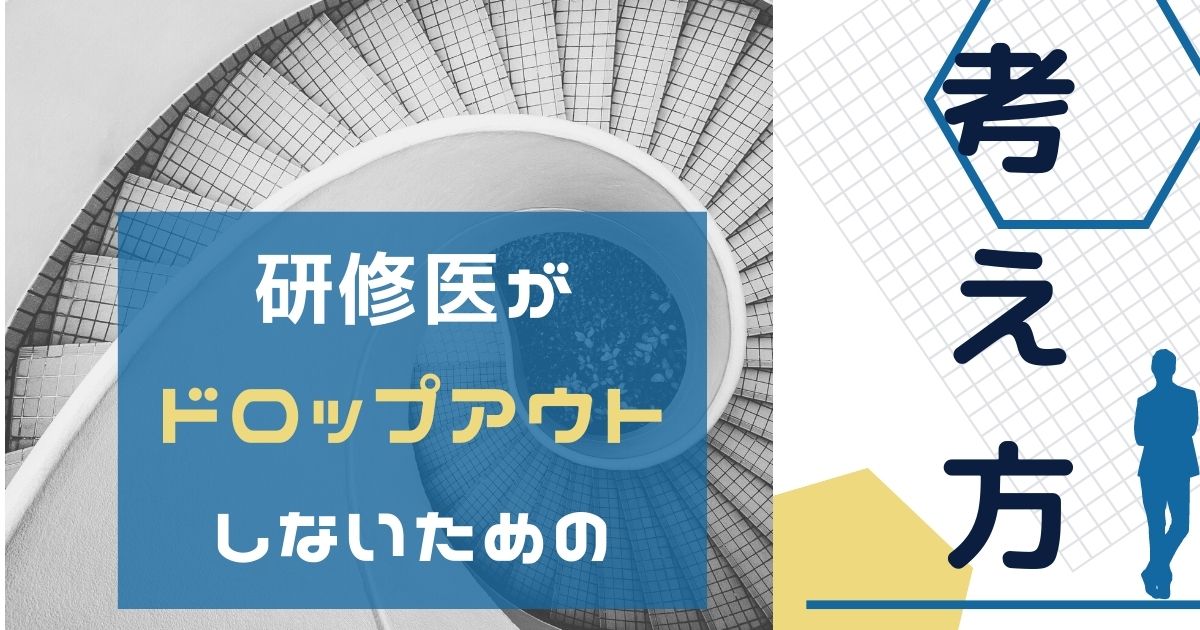こんな悩みを持っている人はいませんか?

この記事を書いている僕も研修医時代は苦労をし、辞めたいと思ったこともあります。
そんな僕も、今では医師歴 約10年。今も初期研修医が勤務するような病院で、働いています。
そんな経験をもとに、「研修医が2年間を乗り切るための考え方」というテーマで記事を書きました。
この記事の結論は、
研修医は特殊な期間なので、うまくいかなくても「医師に向いていない」なんて思わなくてもいい
ということです。では、解説していきます。
研修医の現状

初期研修医としての2年間は、なかなかに厳しい期間です。
初期研修医のうち、25%は研修開始後2か月でうつ状態になるといわれています。
参照元:初期臨床研修における研修医のストレスに関する多施設研究
研修中断する人の割合は全体の1 %ですが、中断に至らない程度の休職者は更に多いと予想されます。
中断の約1/3は病気療養が理由であり、メンタルヘルス上の事情が多いようです。

研修医は特殊な期間だという話

今になって改めて感じることですが、研修医という期間は医師人生の中でも非常に特殊です。
ここからは、医師歴10年の目からみて、研修医の働き方がどれだけ特殊か解説していきます。
①勤務時間について
研修医の勤務時間は、平均約57.5時間/週と報告されています(診療時間+診療外時間(指示なしを除く)+宿直・日直中の待機時間)。

対して、常勤勤務医全体の平均勤務時間は約56.5時間/週です。
平均値としては研修医もそれ以降も似ていますが、研修医は自分にあった働き方を選びにくいという点が異なります。
今後このくらいの勤務時間の環境を選ぶことは可能なはずですし、選ぶ進路によっては平均より短くすることもできます。
さらに「平成28年調査と比較し、比較可能な範囲では、各診療科で週当たり勤務時間は短くなっている」とのことで、今後医師全体として労働時間が改善していくことが予想されます。
参照元:第9回 医師の働き方改革の推進に関する検討会 参考資料3
ポイント
研修医がイメージするほど、長時間の労働は必須ではないかもしれません。
②数ヶ月に1回職場が変わる
研修医は1-3ヶ月に1回、科が変わります。慣れた頃に次の科に変わることを、負担に感じている人も多いと思います。今から振り返っても、この働き方はつらいです。
条件は他の研修医も同じですが、環境の変化に強い研修医=良い研修医という評価になってしまいがちです。
しかし研修医が終われば数年、中堅以降であれば5年以上、同じ職場にとどまって仕事をしていくことになります。自分の中に仕事のパターンができてしまえば、かなり楽になります。

③指導医がいい医師か見分けられない
「人として良くない医師」「指導に向いていない医師」というのは、残念ながら一定数にいます。
医師として生きていく以上、こういった上司/同僚/部下を完全に避けることはできません。
ただいろいろな医師をみた後であれば、「この人は良くない人だ」と分かったうえで付き合うことができます。
医師としての期間が短く、自信がない状況では「自分が悪い」と感じてしまいがちです。
特に研修医1年目の前半で、こういった指導医を引き当ててしまった場合は、かなりの不運です。
同級生と「指導医情報」を共有することは、一つの対策になると思います。このあたりをざっくばらんに話してくれるメンター(先輩医師)がいれば、更に心強いです。

④給料が安い
研修医の給料は安いです。具体的には、下記のとおりです。
1年目の平均給与
大学病院:約307万円
市中病院:約450万円
全体平均:約440万円
参照元:レジナビweb: 病院情報のチェックポイント ~給与・福利厚生~
安いといっても、「研修医の適正な給料はいくらか」という話がしたいわけではありません。
これから給料が上がっていくと、それに伴って働くモチベーションが上がり、ストレスへの耐性が確実に上がっていくという話です。

⑤残業耐性を持っていない
長時間残業をしている指導医をみて、「自分はこうなれない」とコンプレックスに感じるかもしれません。
しかし指導医は、研修医が持っていない残業への耐性を持っています。
それは次の2つです。
・残業代が出ること
・専門分野であること
「きちんと金銭面での対価がもらえる」「興味のある分野である」「将来の自分を助ける直接的な経験になる」という点は、残業がつらいという気持ちをかなり和らげてくれます。
最近は残業代が出る研修病院も増えてきたようで、素晴らしいことです。


⑥給料に見合う仕事ができない(と感じる)
知識や技術が足りないうちは、「自分は給料に見合うだけの仕事ができていない」と感じてしまうことも多いのではないでしょうか。これもなかなかのストレスです。
しかし自分できる貢献が、給料を超える日がそう遠くはありません。
⑦同期と競う最後の期間
これまで大学受験、大学、国家試験と、たくさんの同期と競ってきたのではないでしょうか。研修医は、同じ土俵で競う最後の期間です。
この先は、専門分野や仕事内容など方向性が細分化され、オンリーワンを目指していくことになります(比較がしにくくなってくる)。
だからこそ、マウントをとってくる同期も多いです。
・寝てない→危ないから寝ましょう
・手技/発表をした→これから何千とやるチャンスがあります
・一人で診た→危ないから人を呼びましょう/呼べる環境が望ましいです
大抵、研修医のマウントはこの3つに集約されます。

⑧好かれるタイプが限られる
「研修医として好かれるタイプ」というのは、限られると感じます。
・ハキハキ喋る
・愛想が良い
・積極的にみえる
・短期間に結果を出す/要領がいい
見た目の印象なども関係します。確かにこれらの特徴は、その後の医師人生でもプラスに働きます。
ただ研修医として気に入られなかったからと言って、医師としてうまくやれないわけではありません。
愛想がなくても、淡々と地道に積み上げていくことができれば、十分信頼に値する医師に成長することができます。

ミニマムな目標設定も1つの手段

ここまで、研修医という立場の特殊性を解説してきました。
特殊な環境でうまくいかなくとも、思いつめすぎず、研修医期間の目標をミニマムに設定するのもおすすめです。例えばこんな感じです。
目標①
・とりあえず2年間が過ぎて、修了証を手にできたら及第点。
目標②
・3年目に困らないために、今できることに集中する。これができたら満点。
まず自分の志望科や3年目の勤務先を、ある程度絞ります。
そして「とにかく3年目の勤務先で困らないこと」だけに集中しましょう。
・どんな疾患を診るか
・どんな設備があるのか
・どんな手技が必要か
・自分一人でできること/できないことの判断
このあたりがポイントです。
目標③
・志望科以外の知識を吸収する。
・志望科の技術のうち、3年目ですぐ必要となるわけではないものを身につける。
⇒これができたら満点以上。


本当につらかったら

ここまでの内容は、「気の持ちよう」で乗り切れる場合に限った話です。
本当につらいときは病院の研修担当や産業医、心療内科に相談することをおすすめします。
客観的かつ専門的な意見をもらうということは重要ですし、問題を共有することで状況が良くなる可能性もあります。
ポイント
「つらいときに、周りに助けを求める」というのは、医師として生きていく上で必要な能力です。
医師人生は長いです。研修医を乗り切ったとしても、いつか必ず、人に助けてもらわなければならない日がきます。

まとめ
研修がつらい、ドロップアウトしそう、こう感じたときにおすすめしたい考え方を解説しました。
要点はこちら
- 研修医は特殊な環境
- 研修医としてうまくいかなくても、医師として成功できる
- 目標はミニマムに設定する
- 助けを求める能力は必要

大学病院から個人経営のクリニックまで様々な病院があります。スタッフの雰囲気も家族のようなものから、ビジネスライクなものまで多彩です。
週6日以上働く環境から、週4常勤、アルバイト医師、研究医など、数え切れない働き方があります。
たくさんの科や専門分野があるのは、既にご存じの通りです。

今回は以上です。